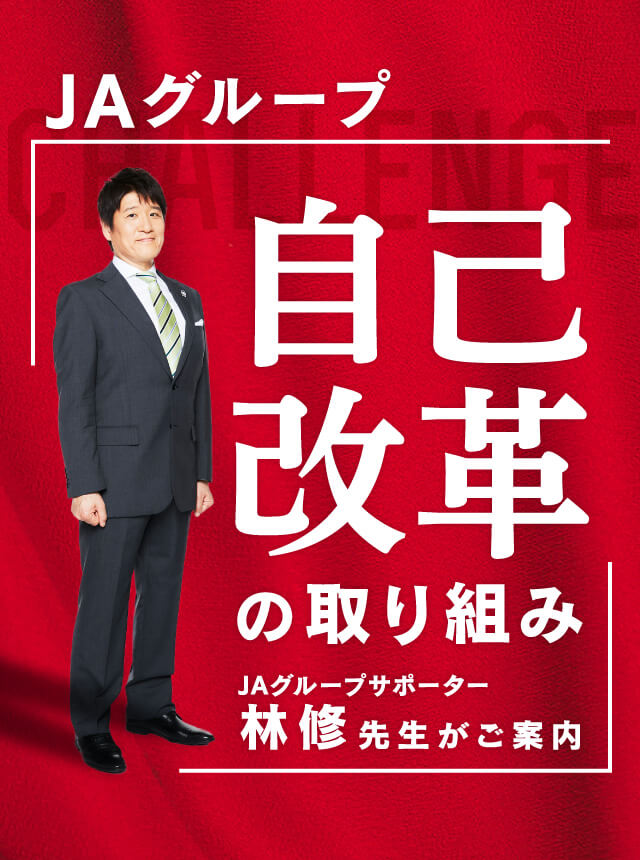
「創造的自己改革」で
一層元気な農業・地域を
全国のJAは、2014年より「創造的自己改革」として「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」を基本目標に、創意工夫ある取り組みを行っています。
多くの地域にとって基幹産業である農業が活性化すれば、関連産業や地域経済にも好循環が生まれ、地域社会全体が元気になっていきます。元気な地域が日本中に増えていくことは、農業者にとっても消費者にとっても、とても幸せなことなのだと思います。
JAグループでは、JAへの理解を深め、
JAをより身近に感じていただけるよう
「JAグループの活動報告書2023」を作成しました。
JAグループサポーターの林修先生による国消国産の解説をはじめ、
農業のさらなる発展・成長や、安心してくらせる地域社会づくりに取り組むJAグループの姿についても具体的な数値や事例でご紹介しています。

